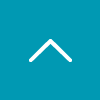効率と非効率のあいだの心地良さ
先日、近所で評判の回転ずし屋が新装オープンしたというので早速行ってみた。店内へ足を踏み入れた瞬間、すぐに異変に気が付いた。いつもは中央ですしを握ってくれていた職人さん達の姿は消え、そのスペースは座席に置き換わっていた。それぞれの座席にはタッチパネルが備えつけられ、これを操作すると注文の品が次々と目の前まで運ばれてくる。慣れた人であれば、食べ終えるまでの所要時間は10~15分くらいだろうか。極限まで効率が高められた状態と言っていいかもしれない。
しかし、出てきたすしをよく見ると、ネタの大きさにはかなりバラつきがあり、箸や手で取ろうとしてもシャリが簡単に崩れてしまうものも混ざっていた。「さてはロボットだけですしを握っているのか」と疑い、厨房の奥へ目をやると、やはり職人さんの姿はどこにも見当たらない。ついでに店内を見回すと、お昼時なのに客数も少なく空席が目立つ。効率が高まって、席が増えたのだからすいているように見えるのは致し方ないところか。しかし、以前はあった大切な何かが失われた気がした。
その数週間後、近所にあるもう一軒のすし屋へ入ってみた。今度はカウンター越しに職人さんがすしを握ってくれる昔ながらのお店だ。内装はきれいにリフォームされてはいるが、間取りや佇まいは大きく変えていないようだった。おまかせ握りを注文すると、すしネタの産地や食べ方について一言、二言の説明を加えたうえで、目の前のすし板に握り寿司を載せてくれる。職人さんが1つ1つ手で握るので、ロボットよりも時間はかかってはいたが、その分長居していてもお店に対する罪悪感のようなものがなかった。談笑する余裕もある。とても、同じ街のすし屋とは思えない。安心したのと同時に、すしを食べている実感も湧いてきた。
もちろん、一概にどちらのお店が良いとは言いきれない。ただ、効率を追求するあまり、心地良さを演出していた部分までもが削ぎ落とされ、ロボットが握るすしをお客さんに食べさせるお店ばかりが増えてしまうのは何だか寂しい気がする。弱点にしか思えなかったようなことが、独自性を発揮し、他にはない強みになることがある。一見すれば、非効率にしか見えない古めかしいことも、目には見えない新しい価値を生み出すことも多い。それゆえに過去と未来の持ち味をうまい具合に重ね合わせた方が、独自性の強い、新たな心地良さを創出できるように思われる。
関連する分野・テーマをもっと読む