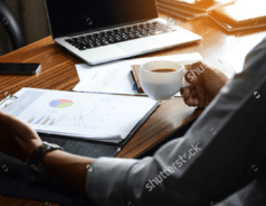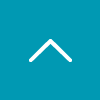SMTRIシリーズレポート 巻頭言
我が国のリアルアセットファンド市場の課題と展望
専門家の視点からリアルアセットファンド市場を分析する
三井住友トラスト基礎研究所は、1988年に「都市と不動産」に関する専門シンクタンクとして設立され、不動産ファンドの運用会社には市場リサーチを、投資家には投資助言を提供してきた。近年では、PPPやインフラ投資分野にも事業領域を広げ、リアルアセットファンドを多角的に分析する専門性を有している。
今般、シリーズレポートとして、各事業領域の専門家の視点から、日本のリアルアセットファンド市場への課題と展望を示すこととした。その序章として、本稿ではレポートを発信するに至った背景と問題意識を整理する。
なお、本シリーズレポートにおいて「リアルアセットファンド」とは、不動産ファンドおよびインフラファンドを指すものと定義する。ただし、不動産やインフラという実物資産を間接的に保有するファンドや実物資産に関わる事業全体の収益をリターンの源泉とするファンドなど、様々な形態が存在することには、予め留意されたい。
都市の課題解決にはリアルアセットファンド市場を通じた民間資金の活用が不可欠
日本における不動産やインフラの整備は都市によりバラつきがあり、大都市でもインフラの整備は重要な課題である。こうした資産については、不動産ファンドやインフラファンドを活用して資本コストの低い投資家が保有し、専門性を有する事業者が運用を担うことで、経済全体の効率性が向上し、日本経済の持続的成長にも寄与する。日本では、資本コストの高い事業会社が本業と関係のない不動産を保有するケースがあり、また自治体によるインフラ保有は財政面を含めて制約が生じている。
このようなファンドを通じた資金循環の仕組みは、政府が掲げる「資産運用立国」の方針にも合致している。国民の金融資産が貯蓄から投資へと向かい、こうした分野へも資金流入が進めば、その恩恵は国民にも還元され、成長と分配の好循環につながる。
リスクリターンの正確な認識と仕組みの工夫で持続可能な投資商品を創出
このような資金循環を実現するためには、多様な不動産およびインフラ資産の本質的価値やリスクリターン特性を的確に把握し、ファンドの構造を工夫することで、投資家の選好と適切にマッチングさせ、投資対象の多様化を図る必要がある。
オペレーショナルアセットやインフラ資産においては、事業運営や周辺事業の収益性が重要な要素となる。形式的に資産を分離するだけでは、事業者のインセンティブが損なわれ、結果として事業全体の収益性やサービス品質に悪影響が及び、持続性が危ぶまれる。
ファンドの仕組みを活用すれば、ローリスク資産には適切なレバレッジをかけてリターンを高め、ハイリスク資産や投資家が取りづらいリスクは、保険や信用補完、他のステークホルダーとの分担によりコントロールが可能となる。
投資家の意識改革が後押しするリアルアセットファンドを通じた持続可能な社会の実現
投資家の意識改革も、投資対象の多様化を進める上で重要な要素である。投資家自身が、裏付け資産の本質的価値とリスクリターンに目を向け、投資商品の特性を正確に理解した上で、視野を広げて投資対象を検討することが求められる。
日本では、低リスク・安定収益を好むコア型投資が主流だが、グローバルにはハイリスク・ハイリターンを志向する投資家も多く、インフレ環境下では日本でもそのニーズが高まる可能性がある。また、投資家には、収益性だけでなく、地域社会への貢献や環境への配慮といった公共的な視点も踏まえた投資判断が求められる。
今後は、制度設計や仕組みの整備、運用事業者の専門性向上、そして投資家の意識改革が相互に作用することで、リアルアセットファンドを活用した不動産・インフラの整備が促進され、持続可能で健全な社会の構築に貢献することが期待される。
関連レポート・コラム
- SMTRIシリーズレポート【我が国のリアルアセットファンド市場の課題と展望】
- 資本が拓く都市の未来 ―不動産ファンドが果たしてきた役割と今後への期待― (2025年10月1日)