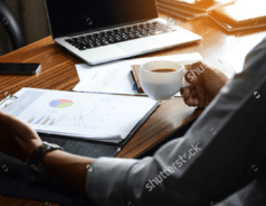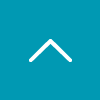私募投資顧問部 上席主任研究員
菊地 暁
不動産投資に迫る人権開示の波
不動産投資市場におけるサステナビリティは、もはや気候変動や自然資本といった環境(E)の課題だけにとどまらない。今や社会(S)の側面、特に人権の尊重や労働環境の整備、地域社会との関係性が投資判断に直結する時代となった。労働環境の不備や住民との摩擦といった企業活動が社会に与える影響は、不動産の資産価値や収益性に大きく反映される。この現実を前に、企業は単なる環境対応に留まらず社会的責任を果たす姿勢を示すことが重要である。こうした背景を受け、2024年9月に発足した
TISFD 1は、企業に対して人権や労働環境、多様性・包摂性などの社会的リスクと機会を、財務的な観点から明示する枠組を提供している。TISFDに基づく情報開示は、企業が自らの社会的影響を可視化し、ステークホルダーとの信頼関係を構築する上で、これまで以上に重要な役割を果たしている。
これまで不動産投資市場では、TCFDやTNFDといった環境関連の開示枠組が注目されてきた。しかしTISFDは環境(E)ではなく、社会(S)、特に人権に焦点を当てる。開発段階では、労働環境の整備、地域住民との関係、使用資材の調達過程における倫理性など、影響は多岐に及ぶ。これら非財務情報を反映させることは容易ではなく、多くの企業にとって新たな挑戦となる。
TISFDへの対応では、人権デューデリジェンスの体系化が特に重要となる。建設現場やサプライチェーンの労働環境調査、児童労働や強制労働の有無確認、契約先の遵法監査を定期的に実施し、潜在的なリスクを早期に特定することで、問題発生前に対応策を講じられる。また、地域住民との対話も不可欠である。開発計画の初期段階からワークショップや説明会を行い、住民の意見や懸念を反映させることで、摩擦を最小化し、社会的許容度を高めることができる。
運用段階では、テナント企業の労働環境やサプライチェーンの人権リスクの監視が求められる。オフィスビルや商業施設に入居するテナントの労働条件や、建材・消耗品の調達先の倫理的適正を定期的に確認することは、TISFD対応の実務として重要である。さらに、施設設計においてバリアフリーやユニバーサルデザインを導入し、多様性・包摂性を確保することも、社会的責任を果たす上で重要である。
これらの取り組みに係る開示は、投資家にとっても有用な情報となる。もし社会的配慮が不十分であれば、住民訴訟、行政指導、テナントの退去、空室率の上昇といった損失が発生し、財務リスクとして顕在化する。また、多様性・包摂性向上による入居者満足度やテナント定着率の改善は、長期的な収益性や資産価値の向上として開示可能であり、これを逃せば機会損失となる。
TISFDは、単なる形式的な遵法や報告にとどまらず、社会的影響を実務的に管理し、非財務情報としての可視化を企業に求めている。マテリアリティ(企業が経営を行う上で優先的に取り組むべき「重要課題」)評価を明確化し、ステークホルダーとの対話を通じて重要課題を特定するプロセスは、情報の信頼性を高める上で不可欠である。
不動産投資市場は、もはや社会的責任を無視した経営が許されない時代に入った。人権や社会的影響の管理を怠れば、短期的な損失だけでなく長期的な機会損失や企業評価の低下を招く。逆に、TISFDに沿った積極的な取り組みは、透明性と信頼性を高め、投資価値を最大化する最強の武器となる。今後の不動産投資市場において、TISFD対応は避けて通れない課題であると同時に、企業が競争優位を確立する絶好のチャンスでもある。
(株式会社不動産経済研究所「不動産経済ファンドレビュー 2025.10.5 No.710」寄稿)